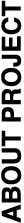
Powered by 東京新聞ABOUT PROJECT
いま、わたしたちのまわりで、
起きていること。
毎日の勉強や、遊びに恋愛、就活。普段の暮らしの中では見えてこないたくさんのできごと。環境のことや政治、経済のこと。友達の悩みも、将来への不安も。小さなことも大きなことも全部、きっと大切な、自分たちのこと。
確かなこと。信じること。納得すること。コミュニケーションや、意見の交換。
あたりまえの自由さ、権利。流れてきた情報に頼るのではなくて、自分たちの目で耳で、手で、足で、感動をつかんでいく。
東京新聞『STAND UP STUDENTS』は、これからの社会を生きる若者たちに寄り添い、明日へと立ち向かっていくためのウェブマガジンです。等身大の学生たちのリアルな声や、第一線で活躍する先輩たちの声を集めることで、少しでも、誰かの明日の、生きる知恵やヒントになりたい。
時代を見つめ、絶えずファクトチェックを続けてきた『新聞』というメディアだからこそ伝えられる、『いま』が、ここに集まります。






