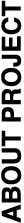年齢という数字について、24歳の夏に思うこと
文・汐見りら
絵・むらいゆうか
「いちひめ、にじょ、さんばば、しかばね」
大学1年の春、新歓の喧騒の中で耳にしたその言葉は、まるで異国の呪文のようだった。漢字に変換すると、「一姫、二女、三婆、四屍」。大学に入学した女子学生が、年次を重ねるにつれてかわいがられなくなる様を表すという。その意味を教えてくれた先輩は「私たちももう三婆だから」と笑っていた。跳ね上げられたアイラインも、きびきびと注文をまとめる姿も、昔話に出てくるような「婆」とは程遠かったのに、誰もその自虐に異議を唱えなかった。私自身も周囲と一緒になって笑っていた気がする。「一姫」である私は、実際、そうすることで簡単にかわいがってもらえた。
「二女」として過ごすはずだった1年は、新型コロナウイルスによってまるごと失われた。気がつけば2021年、私はあっという間に「三婆」の年次に足を踏み入れていた。周囲が就職活動に向けて動き始めるなか、私は留学に行くことを決意する。決意、といっても、それは将来やりたいことが見つからない私にとって、ほとんど逃避だった。

しかし、留学先の語学学校で私の世界は一変した。パンデミックがまだ続く中、海外に出る学生は限られていた。クラスでは私が最年少。21歳だと伝えると、クラスメイトたちは「若いね」「まだ何でもできる年齢だ」と口をそろえた。
「ワーキングホリデーは30歳までできるんだよ。もう行きたい国は決めた?」
そんな質問を投げかけられるたびに私は戸惑った。当時私はもう若くはなくて、自分の人生は、なんとなく先が見えている気がしていたからだ。
けれど年上のクラスメイトたちは、私のイメージよりもずっと多様で豊かな人生を生きていた。キャリアアップのために語学を学ぶ人、パートナーの仕事に同行してきた人、映画に憧れて海を越えた人、定年後に夢だった海外移住を叶えた人。年齢も背景も様々なクラスメイトたちは、誰もが真剣に、楽しみながら学びと向き合っていた。そんな人たちと机を並べて勉強しているうちに、自分のなかの凝り固まった考えが解きほぐされていくのを感じた。もちろんコロナの影響で思うようにいかなかったことはたくさんあったが、あの教室で過ごした時間は私を大きく変えてくれた。
帰国後、4年生になった私は今までになく能動的に動き始めた。卒業に必要なのは卒論ゼミだけだったのに、4年生にして教職課程の履修を始め、新たにサークルにも入会した。
このとき私の背中を押してくれたのは、留学中にクラスメイトがよく口にしていた言葉だった。
” Age is just a number. “
── 年齢なんてただの数字。
一度そう思えたら、それまで周りに流されて過ごしてきた反動のように、やりたいことがあふれ出して止まらなかった。「四屍」なんて、とてもじゃないが当てはまらない、目まぐるしい日々。楽な生活ではなかったけれど、これまでで一番生きているという実感があった。

さて、ここでこのエッセイが終わればもっと爽快なのだろうけれど、人生はそこまでシンプルではないらしい。
留学が人生における第一の岐路だとするなら、大学院進学は第二の岐路だった。前述のやりたいことは全部やるぞ!キャンペーンの最中、もっと学びたいと思うことがたくさん出てきて、私は修士課程への進学を視野に入れ始めた。大急ぎで入学試験や奨学金の情報をかき集めて、それがどうにかクリアできそうだというところで、私の前に立ちはだかったのが「ライフプラン」という壁だった。
恥ずかしながら私は、ぼんやりとした年齢への規範に囚われていた反面、それを自分ごととして冷静に考えるということを全くしてこなかった。
修士課程で2年間を過ごすことは、就職する時期も2年後ろ倒しになることを意味する。私はそれ自体を大きなビハインドだとは感じていなかった。ただ、その後に経験するかもしれない転職、結婚、出産などのライフイベントのことを考えた途端、急に焦燥感に駆られはじめた。目の前の選択が遠い未来の選択肢にも影響を及ぼすことを思うと、気軽に答えを出せるものではない。特に出産に関しては、女性として、どうしても身体的なタイムリミットを意識してしまう。ただの数字、だとやっと思えるようになったはずの年齢が、再び大きな問題として現れたのだ。
結局私は進学を選んだけれど、修士課程2年生の今でも、この問題への折り合いはつけられていない。
ライフプランは、院生同士の会話でもたびたび取り上げられるテーマだ。博士課程に進学するか否か。もし進学をするとして、キャリアをどう設計していくのか、金銭面はどうしたらよいのか。そんな話をしていたとき、ある男子学生が何気なくこう言った。
「でも女子は、研究の道がうまくいかなくても、いざとなれば結婚できるからいいじゃん」
私は最初、その発言にとても憤った。女性研究者が抱える複雑な思いを、取捨選択の痛みを、そんな言葉で片づけないでほしいと思った。
でも今は少し、違う視点も持てる。男性として生きている彼もまた、私とは別のベクトルで、年齢と理想像、社会的な期待の間で苦しんでいたのだろう。
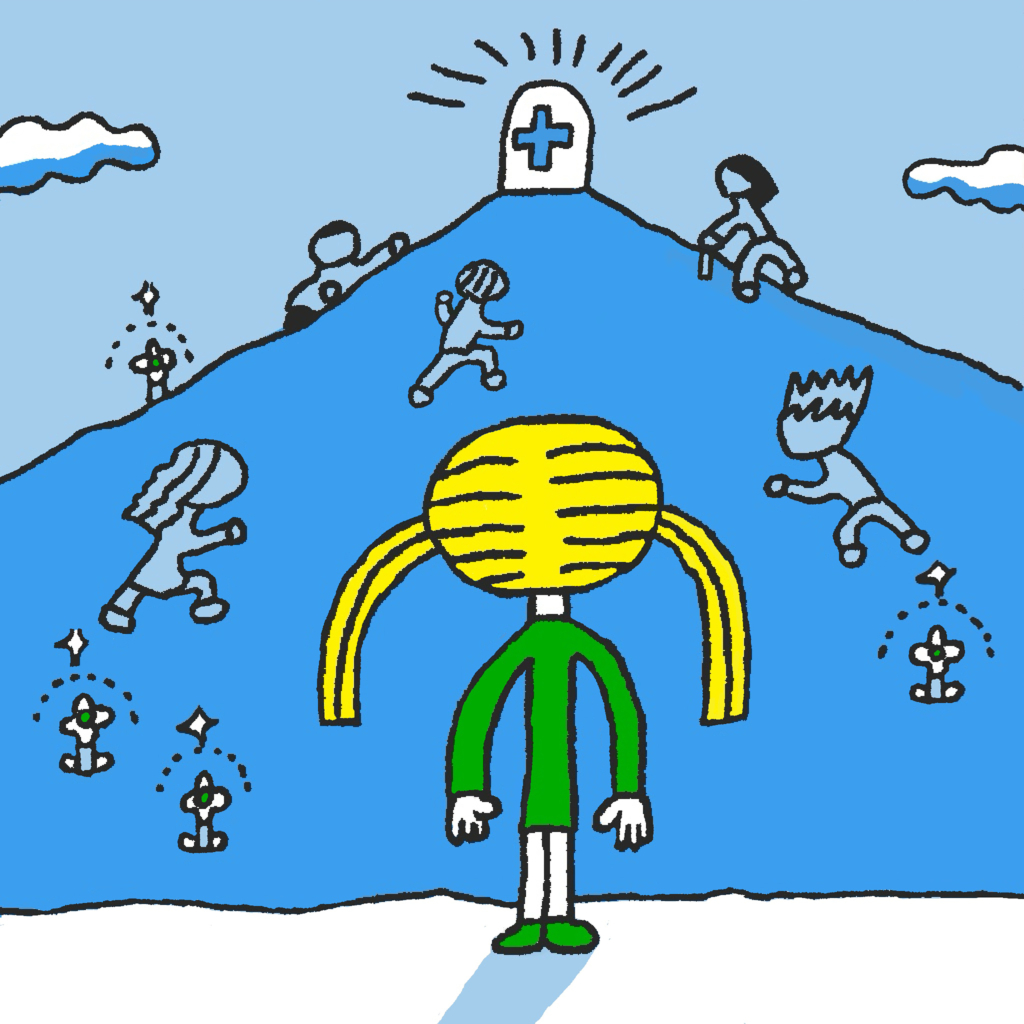
心に靄(もや)を残したまま、今年もまた春が来て、期待と緊張を抱えた様子の新入生たちがキャンパスにやってきた。気がつけば「四屍」から2年が過ぎて、私はゾンビになることも、劇的に生まれ変わることもなく、相変わらずひとりの人間として悩みながら生きている。
生きている限り、人は誰しも平等に年を取る。年齢にまつわる葛藤から自由になることは、きっと不可能に近い。少なくとも私は今、”Age is just a number.”と、昔のように単純に口にすることはできない。その number は私の人生に関わる、とても大切な数字だから。
でも、だからこそ、その年をどんなふうに過ごすのかは、社会のジャッジではなく私自身が決めていきたい。これからも考えることをやめずに生きていくなら、いつか年齢は私にとって足枷(かせ)ではなく、思考の蓄積を示す誇るべき証左になるのかもしれない。今はそう信じて、25回目の夏を過ごしている。
2025年8月13日
※ エッセイへのご感想やご意見がありましたら STAND UP STUDENTS の公式インスタグラム へ DM でお送りいただくか、匿名でも投稿できるフォームにお送りください。STAND UP STUDENTS では、今後も、学生たちがさまざまな視点で意見や考えを交換し合える場や機会を用意していきます。お気軽にご参加ください。

- 汐見りら
- RIRA SHIOMI
大学では文学を、大学院では教育学を専攻。 最近は少し遠い図書館巡りを楽しみながら、修士論文を執筆している。 同名で歌人としても活動中。
----------
イラスト:むらいゆうか
https://www.instagram.com/mriyuka/