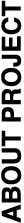『大人』という症状
文・歌床なな
絵・藤本将綱
20歳(ハタチ)になった。
「誕生日おめでとう!」「お酒解禁おめでとう!」「大人の仲間入りだな、おめでとう!」…。幼いときあんなに憧れていた “大人” になってしまった。
“大人”になった私の感想は「子どものままでいたい」であった。もちろん、学生生活(いわゆる人生の夏休み)が楽だからというような不純な理由ではない。
大人になればなんでも手に入ると思っていた。宿題の代わりに趣味の時間ができるし、近所で遊ぶだけで足りなくなるお小遣いがゲームの1つや2つなんてすぐに買えるようなお給料になる。
でもそれは “大人” に夢を抱いた子どもが見た幻だった。なんでも持っている大人の正体は、夢を見ることをあきらめた寂しい人だった。
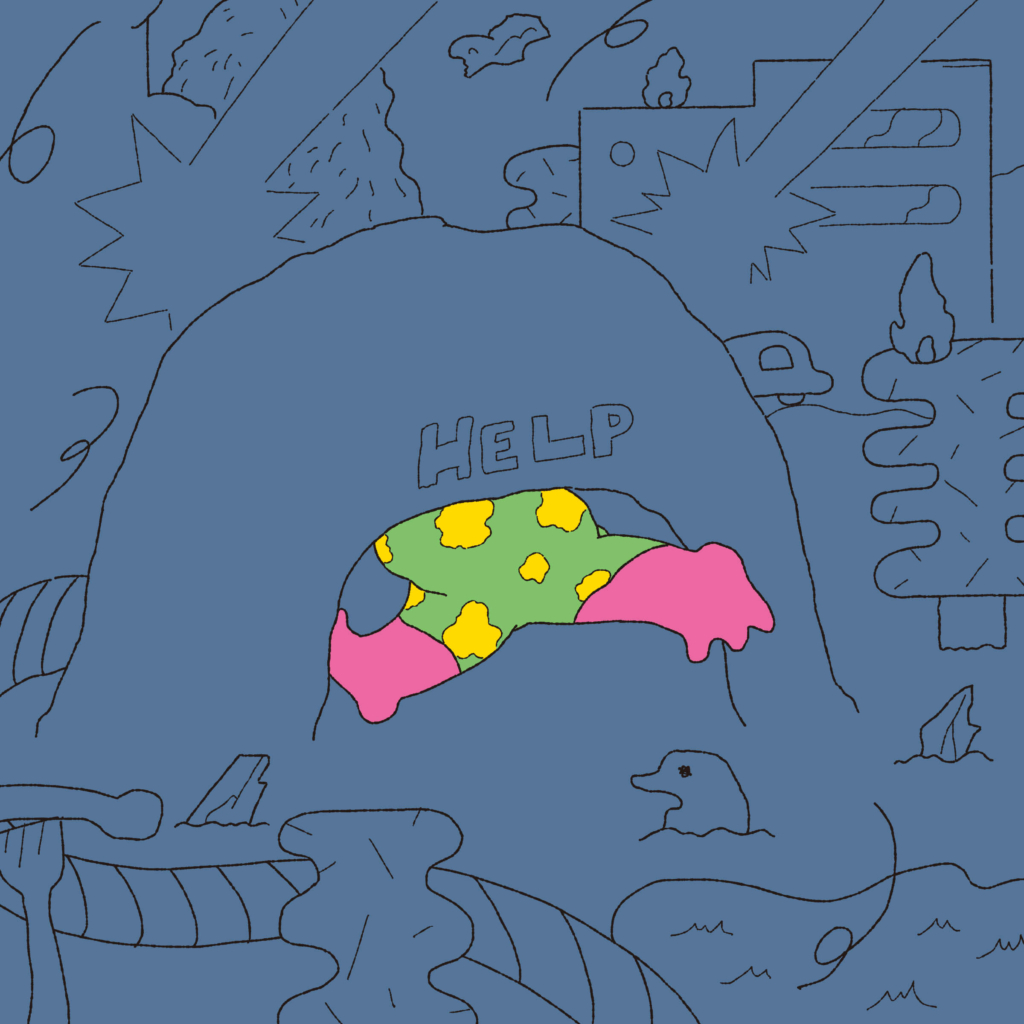
人は生きている中でいろいろなことを経験し、学び、賢くなる。いや、賢くなったつもりになる、と言った方が正しいと思う。いろいろな経験や学びの中で価値の尺度を絞っていき、立派なバイアスを手に入れる。私はこれを「計量カップ」のようだと思う。なんでも持っているはずの大人は、たった1つの計量カップしか持っていないという事実に気が付いたのはつい最近だ。
計量カップとは具体的に何か。例えば、こんな話をしたらわかりやすいだろうか。
あるところに、花が好きな女性がいました。彼女は花が好きなので、よく花屋へ行きます。花屋からの帰り道、知り合いに会ったので、買った花を見せました。すると、その人は言いました。
「わぁ、素敵」
彼女は、家へ帰ると買ってきた花を庭に植え替えました。毎日水をやり、庭の手入れをし続けました。
ある日彼女は、この間、買った花を褒めてくれた知り合いを家に招くことにしました。知り合いは家に上がって庭を見るなり言いました。
「まぁ、とっても素敵」
1ヶ月後、彼女のていねいなお世話の甲斐あって、庭はたくさんのきれいな花で溢れました。彼女は、その中のいくつかを摘んで花の冠を作りました。そして、それを被って街を歩きました。再び知り合いにあったので彼女は冠を自慢しました。
すると、知り合いは、素敵と言う代わりに笑いました。それも馬鹿にするように。
大人の価値の尺度は計量カップのようなものだと思う。
「知り合い」の計量カップには “花が素敵” という気持ちがだんだん溜まっていく。買った花を見たとき、彼女の計量カップのメモリは 50ml になった。庭を見たとき、計量カップのメモリは 50ml から 100ml へ上がった。しかし、カップから溢れたら、もう訳がわからない。わからないことは、笑い飛ばす。それが大人になるということだと思う。
子どもになったつもりで想像してほしい。街中で花の冠を被った女性を見かけたら、どう思うだろうか。「かわいい」「私も欲しい」そう思うのではないか。あるいは、子どもでも、おもしろおかしく笑い飛ばすか。
もし、後者だったら、それは周囲の責任だ。学校や家庭での経験が、あなたの計量カップ作りを助長したのだと思う。
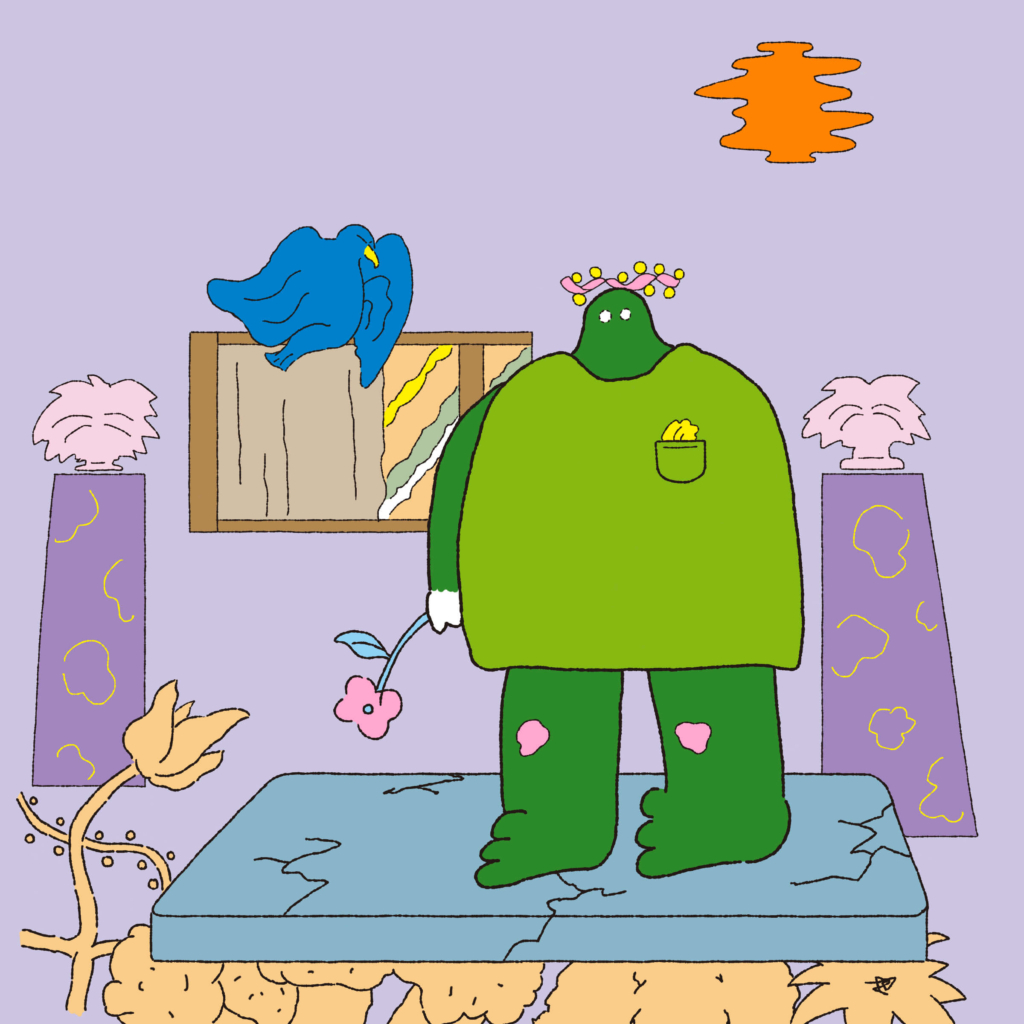
話を戻す。前に「人は生きている中でいろいろなことを経験し、学び、賢くなる」と書いたが、「賢くなる」の正体は、自分の心に計量カップを組み込むことだった。でも、希に、賢くなりきれなかった大人もいる。
賢くなれれば簡単だ。計量カップから溢れたら笑えば良い。一緒になって笑う仲間を増やせれば、もっと良い。しかし、賢くなれなかった大人は、不良品として扱われたかのようなみじめな思いをする。
みんなが笑っていても笑えない。むしろ、笑われている人やものが素敵にさえ思えてしまうことがある。不良品は、やはり苦しまなければならないのだろうか。そう思うと同時に、不良品なりのプライドが芽生えて、計量カップを持たない自分を大事にしたいという気持ちもある。
私は先日、小学校へ教育実習に行った。学校とは計量カップを持つ大人が、そんなものなど持ち合わせていない子どもを教育するという恐ろしい現場だ。そう思ってしまった。
「HさんとSさんは揉め事が多いから注意して」
「Kくんはマイペースであんな感じだから放っておいて良い時もある」
初日の放課後、担任の先生に言われた言葉が引っかかって、モヤモヤを抱えたまま1ヶ月を過ごした。
しかし、そんな1ヶ月でも収穫はあった。
Hさんは、自分が兄弟の中で1番勉強ができないことを嫌がり、何か褒めて欲しいと言いに来るような子だった。Sさんは、自分の気持ちを言葉にすることが下手っぴな子だった。
Kくんは、気が向くと、彼にしか見えない世界を一生懸命伝えようとしてくれる子だった。
彼女らは、大人の計量カップという勝手からこぼれ落ちた子だった。
夏休み、期間限定で小学校の学童をお手伝いしたときにも同じようなことがあった。私がはじめてシフトに入った日、レギュラーの方から「名札にシールが付いている子は気を付けて」と言われた。
私がお手伝いした学童では、手がかかる子の名札に小さな丸いシールを貼っているようだった。確かにシールが貼られた子たちは活発だった。でもそのシールも所詮、大人が計量した “手のかかる度” が高い子に貼られたものだった。
両親と離れている時間が長いと寂しがる子が発する「抱っこして」。それが面倒くさいから。ダンスをがんばっている子が褒めて欲しくて膝の上によじ登ることで喧嘩がはじまるから。だから貼られたシールだった。
彼らの行動は、お弁当の箸を忘れた普段おとなしい子に割り箸を取ってきてあげることに比べて “手がかかる” のだ。でも、“手がかかる子” の背景は計量カップ無しで関わらないとわからない。
「抱っこして」に応えたから「今日の夕飯マックかなぁ…」の寂しさを知れた。膝の上に乗せたから「将来ね、アイドルになりたいからダンスはじめたの!今度発表会があるけどママ来れないから見に来てよ!」のがんばりを知れた。
夕飯は作ってあげられないけれど、抱っこしながら一緒に宿題をした。
ダンスの発表会には行けないけれど、握手会とサイン会の練習をした。
彼らもまた、大人の計量カップという勝手からこぼれ落ちた子だった。
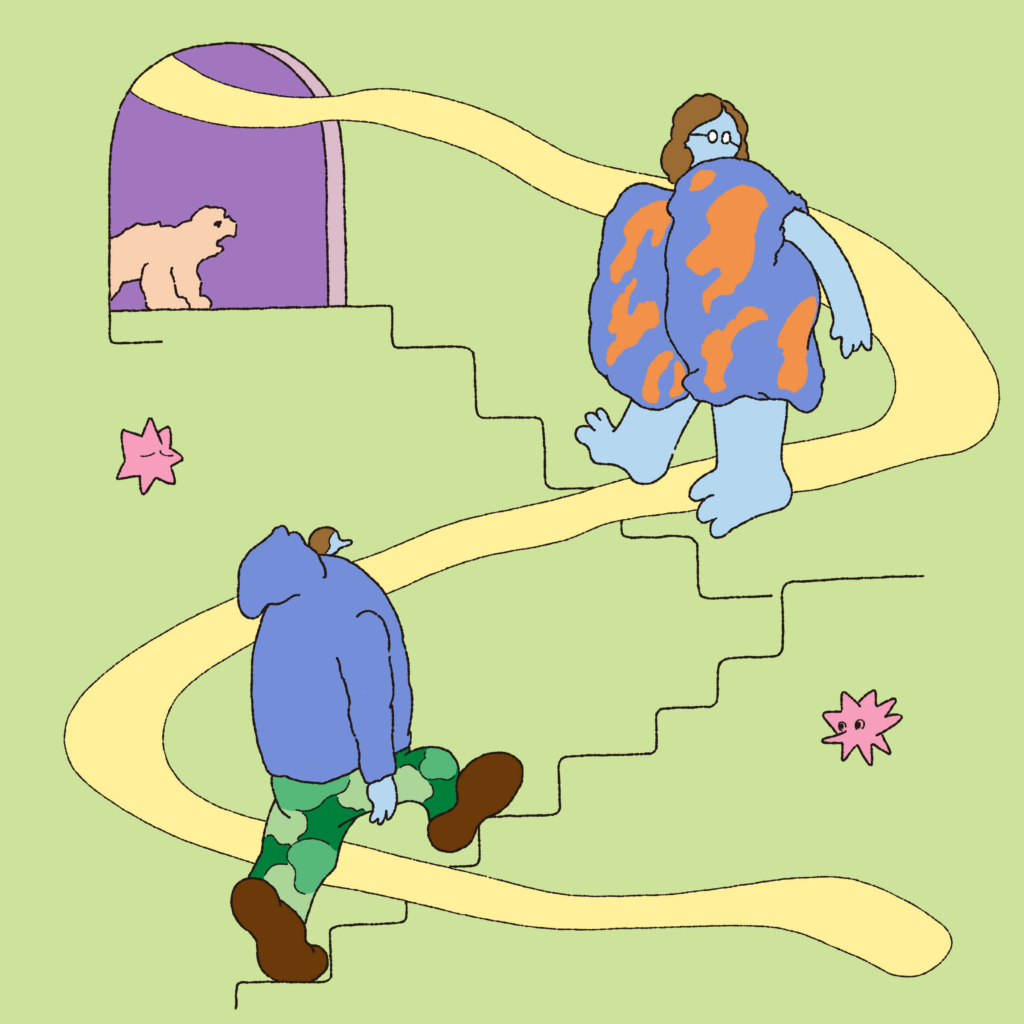
私は昔、大人に憧れると同時に、少しの嫌悪感も抱いていた。計算ドリルを解いていて「ここが分からない」と言うとていねいに教えてくれるのに、「どうして勉強しなくちゃいけないの?」と言っても答えてくれる大人はいなかった。
当時の私にとっては、どちらも同じような質問だと思っていたが、大人の計量カップで考えると雲泥の差があったようだ。計量カップ内で答えられる前者と、計量カップから溢れてしまう後者。
“大人”はよく、子どもの見る夢を「素敵だ」と言う。でもそれは「子どもが見る夢」だから素敵と言っている。“大人” でもそんな夢を見たいと願ってしまうこともある。でもそれは、計量カップの外にある。だから諦めるしかない。
しかしどうだろう。心の中から計量カップを取り外せた時、“大人” でもきっと同じように夢を見られる。計量カップが無ければ、そこから溢れるものなんてこの世に存在しないのだから。でもきっと、一度でも計量カップを心に組み込んでしまった人たちにとって、それはとても勇気が必要で、不便で、苦しいことだと思う。
だから20歳の私は今、この文章を残す。
かつて子どもだった大人の方へ、これから大人になる子どもたちへ、大人になりたくないと足掻く私たちへ。桃源郷でもいい。大人でいることがつらくなったとき、全ての人に逃げる場所がありますように。あわよくば、この文章がそうでありますように。
2025年3月10日
※ エッセイへのご感想やご意見がありましたら STAND UP STUDENTS の公式インスタグラム へ DM でお送りいただくか、匿名でも投稿できるフォームにお送りください。STAND UP STUDENTS では、今後も、学生たちがさまざまな視点で意見や考えを交換し合える場や機会を用意していきます。お気軽にご参加ください。

- 歌床なな
- NANA UTAYUKA
※ 歌床ななは今回のエッセイのためのペンネームです
----------
イラスト:藤本将綱
https://www.instagram.com/fujimoto_masatsuna/