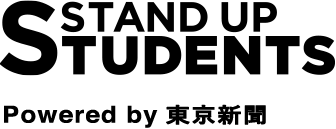01
なぜ私たちはサバイバル
しないといけないのか
みなさんが生まれてくる2000年代になると「生きづらさ」の上に政治・経済の大きな変化が加わってきます。それが「新自由主義=ネオリベラリズム」と言われる問題です。つまり「自己責任論」に基づくいわゆる「小さな政府」という路線が、日本の政治の中心に踊り出るようになりました。その立役者が当時の首相・小泉純一郎さんです。ご存知の方も多いと思います。「構造改革」「官から民へ」という言葉を使って「自己責任」を強調しました。行政サービスに頼るのではなく、自分に必要なものは自分の力で獲得していく。必要なものを公的支援で獲得するではなく、自分の稼ぎによってマーケットで調達する。そんな主張を強く推し進め、市場の公的規制を緩和させることで、日本は「小さな政府」を目指すようになりました。
「小さな政府」とは、租税負担率が低い代わりに、全GDPに占める国家歳出の割合も小さいという行政のあり方です。セーフティーネットには穴が開き、リスクに対しては個人で対応しなければなりません。そして、「小さな政府」の社会では、公務員の数が少ないのが特徴です。1000人に対する公務員の数で見ることができるのですが、ヨーロッパの平均とされるイギリスで78人ぐらい。北欧諸国は100人を越えてきます。最も小さな政府と言われているドイツでも55人ぐらい。「公務員の数が多い」と思われている日本はさらに少ない38人ぐらいと言われています。

私は「小さすぎる政府」というのが的確だと思います。地方自治体では正規公務員が減って、災害が起こったらなかなか復旧に至らない。熊本でも能登でも、災害からの復旧にものすごく時間がかかっていますよね。あれは、いろいろな理由がありますが、地方行政の弱体化という側面が非常に大きいと思います。いくら窮地に陥っても、社会も国も行政も助けてくれないというのが日本という国のあり方になっているわけです。一度失敗してしまうとドーンと滑り台のように下に落ちてしまう「恐怖」が浸透していますよね。なんとか失敗しないようにサバイバルして生き残らないといけない感覚が2000年以降に生まれたみなさんの中に強くあるわけです。それが「自己責任論」として語られていくようになるわけなんです。
今の学生たちは私たちの時代の学生に比べて、授業にちゃんと出席します。成績を気にします。就活に向けてしっかりと点数を取っておかないといけないという気持ちが大きいですよね。点数が低い場合のリスクをしっかり考えているんですね。


02
「ひろゆき」が冷笑と
論破を繰り返す社会で
そんな中で登場するのが「ひろゆき」という存在です。ひろゆきさんのことを知っているという学生は多いかと思います。私の息子の中でも流行っているのか「それってあなたの感想ですよね?」なんて親に向かって言ってくるくらいですから(笑)。「ひろゆき現象」なるものはご存知だと思います。
では、ひろゆきさんが言っていることっていうのは一体どういうことなのか。彼の本の表紙や見出しの中には「ライフハック」「仕事術」「裏技」「ショートカット」という言葉が多用されています。「うまくコスパよくやっていこうよ」「自己改造して社会的成功を勝ち取ろうよ」というのが彼の技であり言い分なんですね。
つまり「サバイバル社会」を変えていこうとするのではなく、サバイバル社会をいかに効率的に戦略的に生きるかを教えますよというのが彼のスタンスなわけです。旧来の日本はオワコンと捉え、冷笑と論破を繰り返し、「ズルくてもいい」「そんなの関係ない」「問題が起きたら逃げればいい」というテクニックで自己責任社会を生き抜く方法というのが、ひろゆきさんの本に多く書かれていたことでした。
それがある種の「救い」になっているのだとも感じます。サバイブするためにコミュニケーション能力を磨けと言われてきた90年代から2000年代に対して、コミュ障と呼ばれるひとでも、ひとりでインターネットを使って起業してうまくやれるよ、その方法を全部教えるよ、逃げればいい、というひろゆきさんの存在が、生きづらさを抱えてきたひとたちにとってある種のカリスマになっていった。

新自由主義社会になってから20年以上が経ちましたけれど、根底には常に「生きづらさ」という問題があって、そしてさらに激しい「サバイバル」という環境に晒されているのが、みなさんの世代であり、「自己責任論」というのが大前提になってしまったのが今の社会なんです。2024年の都知事選で起きた「石丸現象」も似ていますが、サバイバル社会を「うまく乗りこなそうよ」という方向に日本が傾斜しているように見えるのです。私はそれは問題だと感じていて、政治学者として、この問題を乗り越えたいと思っています。




03
これって自己責任でしょ?
さて、ここで問題になってくるのは「自己責任」という言葉です。自己責任って実は古い言葉ではないんです。比較的新しい概念で、いつ公の場で使われるようになり、政治の言葉になっていったのかというと、これには明確な起源があります。今から約20年前、2004年に起きた「イラク人質事件」です。
当時の首相・小泉純一郎はアメリカ側に味方してイラクに自衛隊を派兵します。するとアメリカが優位になるのですが、正面から戦っては勝てないと考えたイラクは一種のゲリラ戦ともいえる人質作戦に出るわけですね。3人の日本人を誘拐し「自衛隊を撤退させないとこの人たちを殺すぞ」と、さまざまな要求してくることになります。結果、日本では大騒ぎになるのですが、そこである政治家が「イラクは外務省が渡航禁止にしているのになんで行ったんですか?」と言ったわけです。となるとこの3人に対して「勝手に行ってみんなに迷惑をかけた」とメディアや世論がバッシングをしはじめるんですね。

そこでさらに当時の環境大臣だった現東京都知事の小池百合子さんが言うんです。
「一般的に危ないと言われている所にあえて行くのは自分自身の責任の部分が多い」と。
この「自己責任」発言が拍車をかけ、日本に戻った3人の家族を含むバッシングが広がっていくんです。3人のうちの1人は「人質に取られていた時よりも日本に帰ってきてからの方が怖かった」と発言し、一時期引きこもりになってしまったと言います。これが「自己責任論」のはじまりとされています。
実はこれ、日本だけじゃなく諸外国も同じように人質を取られて、無事戻ってきてはいるんですけれども、こんな風にバッシングが起きたのは日本だけだったそうです。
もうひとつ「自己責任」を語る上で大事な事件を紹介します。2018年にタイで起きた洞窟遭難事件です。7年前なので覚えているひともいるかもしれません。コーチ含む地元のサッカーチーム13人が、肝試しで洞窟に入るのですが雨季で水位が上昇して出られなくなってしまうんですね。非常に過酷な救出作業で、全員助かるんですが、1名のダイバーが救助中に死亡。さらに、大量の水をポンプで吸い上げることで周囲の樹木や畑に根枯れなどの被害が出てしまうんです。このニュースを見て「イラク人質事件」を思い出した私は、救出後のコーチをはじめ、子どもたちのことが心配になったんですが、タイの中でバッシングはほとんど起きませんでした。みんなが「よかったね」って言っていたんですね。その時に「日本はどんな社会になってしまったのだろう」と、身震いしたんですよね。日本の感覚の方が国際的にはおかしいんだというのを気づかされた事件でした。


04
人生とは奇跡と偶然の
連続でしかないはずなのに
政治学者として、さまざまな政治家と対峙し、政策にも関わる機会が多かったのですが、「政策だけでは無理だな」と感覚的に気づいていくんですね。どれだけいい政策を出して実現したとしても、本当に問題が解決されるのかということに対して懐疑的になってしまったんですね。もちろん関わる以上「政治」に対して努力はします。一生懸命取り組みます。でも、もっと根本に「人間観」の問題があるなと感じるわけです。
人間観にメスを入れないと前に進まないし「生きづらさ」やサバイバル社会の「閉塞感」が解消されない。「次の世界」を描けないのではないかと考えるようになって、最近は政治学と並行して「利他」という研究を進めていて、「新自由主義社会」を乗り越えるための「人間観」を考えるようになっていきます。
なぜ日本人は「バッシング」してしまうのか、というのを仏教や古い書物から突き詰めていくと、人間は「業」や「縁」で少しずつ変容していくものだということがわかるんです。つまり「いつあなたが人質になっていてもおかしくなかった」わけで「そのひとであった可能性があった」ということを自分に開くというのが、「自己責任論」を乗り越えるための「人間観」として非常に重要だと思っています。
どんどん話は哲学的になっていくのですが、哲学者の九鬼周造(くき・しゅうぞう)さんの『偶然性の問題』という本も、「自己責任論」の限界を考える際に重要だと思っています。

私たちは、「自分らしさ」を自分の能力で構築してきたと考えていたりしますが、「それって本当ですか?選んだのではなく、偶然与えられたものではないですか?」と九鬼さんは言っているんですね。生まれてきた時代や親や母語、生まれ育った場所、自分の顔かたちなど、私の人格を構成する大事な部分は、選んでないですよね。自分の意思とは関係なく、偶然付与されたものです。
人類の誕生から今日まで、奇跡と偶然の連続でしかないんですね。
私という存在は、無かったことの方が可能性としては大きかった。でも近代を生きる私たちは、自立した個が理性的に思考し、意思をもって様々なものを選択していると考えています。そして、自分で選んだことには、責任が伴うと。これが自己責任論につながる近代的な人間観ですが、どこかおかしいですよね。だって、私たちは自分の存在に関わる大半のことを自分の意思で選んでいないのですから。自分に偶然与えられた環境が、今の自分であることに大きな影響を与えていますよね。
ここにいる大学生のみんなもそうです。多くのひとは、今の大学に行けたのは「がんばってきたから」、行けないひとは「がんばってこなかったから」と思っている部分があるのではと思います。もちろん大学に入学するには、さまざまな努力をしたと思います。それはとても大変だったっと思いますし、私も勤務先の大学に入学してきた学生には「よく頑張ったね」と、その努力をたたえるようにしています。しかし、大学には入れたのは、自分の努力だけによるかというと、そうは言えません。塾に行ったり予備校に行ったり、自分の勉強部屋を持てたりしたのは、そのようなことにお金をかけることのできる家庭に生まれたからという側面が大きいですよね。
一方で、「がんばりたくても貧困で自分の部屋や勉強机がなかった子どもたち」とか、「何かの理由で学べなくなったひとたち」もいます。その人たちを「自己責任だ」と片づけてしまうこの社会の方が「虚構」に感じるんですね。
私たちの生はあくまで与えられているものであって、「偶然性」というものを無視して、いまの自分のステータスがどうだっていうのを考えられないと思うんです。
そこで、この授業の冒頭に戻りたいんですが、私が自分の人生を学生時代までさかのぼっていくと、私の岐路はあの時の出来事に行き当たるんです。
インドネシア語を勉強したい彼女に同じクラスになることを拒否されて、「インドネシア」の「ネシア」を取って「インド」を選んだあの出来事なんですよ(笑)。
つまり私が徹底的に疑っているのは自分の「意思」です。英語で言うと「WILL」です。
本当に私たちは意思を持って自分の人生を選んでいるのか、ということです。もちろん意思自体はありますよ。今日は晩ごはんにラーメン食べたいなとか。でも意思だけで生きていないんですよね。たまたま好きになっちゃったひとがいて、大学どうしようってなって、インドネシアじゃなくインドを専攻して留年してナショナリズムに興味が湧いたタイミングでたまたまインドが右傾化して、インドに行った。
ここに「意思」の介在があまりないように思うんですよね。どちらかと言うと流されてきた。でも、その方が信じられる。
その世界の方が豊かだというのが私の根底にはあります。
となると「意思」「選択」「責任」がセットになった「自己責任論」における人間観への懐疑がわいてくるわけです。「意思」「選択」「責任」だけで人間は生きているわけではない。



05
「愛した」と
「愛しちゃった」の違い
ここで私が学生時代にイヤイヤやってきたヒンディー語が活きてくるわけです(笑)。
3年もインドに暮らすと何とか話せるようになるんですが、ヒンディー語を学ぶとまず最初につまずくのが「主格」と「与格」の区別なんですね。

「主格」はわかりやすいんです。日本語で言うと「私は」「私が」ではじめるものです。それに対して「与格」は「私に」で話しはじめる会話ですね。例えば日本で「私はうれしい」というのは主格ですが、インドでは「私にうれしさが留まっている」という与格を用いるんです。
「I LOVE YOU」もそうです。ヒンディー語では「私に愛がやってきて留まっている」という言い方になるんです。若干ロマンチックですよね(笑)。好きになろうと思って好きになるのではなく、好きになっちゃったっていう感覚です。宇多田ヒカルさんの「Automatic」という曲がありますが、あの曲がまさに与格的です。「側にいるだけでその目に見つめられるだけでドキドキ止まらない It’s Automatic」。つまりドキドキしたくてしているわけではないんです。行為はすべて意思には還元されません。自分の意思を超えて、好きになっちゃったり、ドキドキしたり、涙がこぼれたりする。それが人間ですよね。ヒンディー語では、意志に還元されない状態や行為を表現する際に与格を用います。
例えば「私はこう思う」ではなくて「私にはこう思える」っていう言い方をする時がありますよね。電車に乗っていて窓から銭湯の煙突が見えた時、懐かしいなとか、昔、親と一緒に銭湯に行ったなとか、そういえば最近親父元気かなとか。これって私が意図して親のことを考えようとしていないですよね。となると「I think」なのかって思いますよね。私の中に考えがやってきて巡ったり、留まったりしていると思う方が「考える」よりも多い気がするんです。どうですか? そう考えると、あまり自分って「I think」してないなって思いませんか?
むしろ「主格」で物事をコントロールしている時の方が嘘っぽいなって思うわけです。
企業などの謝罪会見を見ているとわかるんですが、幹部が出てきて「申し訳ございませんでした」と頭を下げていて「よし、許そう」ってみんなならないと思うんですね。むしろ「許せない」って思う。
あれはつまり主格による謝罪なんです。考えの中で「謝るのが正解だな」って思っているひとたちです。それに対して私たちが謝罪を受け入れる時っていうのは、ごめんなさいって言えないくらい震えてしまったりとか、与格的な状態のひとを見た時に私たちは「本当に悪かったって思ってるんだな」と感じて、その謝罪を受け入れようと思うわけです。
となると主格を構成している「意思」というのは、少し疑った方がいいのではないかと思うわけです。意思ではコントロールできないということが多いというのがヒンディー語の与格構文に現れた人間観です。その方が人間にとって本質的ではないかと感じるんですよ。同世代の哲学者の國分功一郎(こくぶん・こういちろう)さんが言っている能動態と受動態のあいだの「中動態」の存在も、与格とほぼ同じ意味といえます。
私の生まれる前にヒットした古い曲ですが、「愛して愛して愛しちゃったのよ」という曲があります。ここで大事なのは、「愛した」と「愛しちゃった」の違いですよね。意思が介在する「愛した」に対して「愛しちゃった」には、本当は愛してはいけないのに、どうしようもなくてそうなっちゃったっていう意味ですよね。私はこっちの方が本当の愛に感じてしまうんですよね。「〇〇しちゃった」っていうのが与格的で重要で、人間の本質なんだと思うんです。
さいごに
サバイバル社会で「自己責任」という
世界観を脱することはできる
何をみなさんに言いたいかというと、「意思」によっていろんなものを決定していくという世界から、「ちょっとだけ離れてみませんか?」ということです。

1995年以降に生まれた「生きづらさ」という底流の上に加わった、この「サバイバルしないといけない新自由主義」の中で、さらに「現実感がない」という非常に大きな問題が横たわっている「意思」「選択」「責任」を求められる「自己責任論社会」の中で、わたしたちは生き残るためのスキルを身につけないといけない。
その世界から、ちょっとだけ離れてみませんか。
イギリスの文化人類学者のディム・インゴルドがすごくいいことを言っています。
「輸送と散歩は違う」という言葉です。
現代人の生き方は「輸送」になっていませんか?ということです。私たちの多くは子どもの頃から「いい大学に行くためにはいまのうちに勉強をしなければいけない」とか、「遊びたいかもしれないけれどちゃんと塾に行きなさい」と言われるわけです。つまり受験や進学という目的のために「いまを犠牲にしろ」と言われているわけです。
「塾」は、最短で目的地に行ける方法を提供してくれる。そしてみなさんのように大学に行くと今度は就職するためにいろいろなスキルや経験を身につけろと言われて、また「いま」を刈り取られるわけです。
今度は「就職」するとキャリアアップのためにと「いま」を刈り取られ、さらにキャリアアップすると「老後のため」にと刈り取られ、老後になると死んだ後のために、と「いま」を刈り取って、常に「いま」を未来の投資に使われる。「いま」がずっと犠牲にされる。
それを私は「未来の植民地」という言い方をしています。
「未来」が「いま=現在」を刈り取ってしまうことで、私たちは現在を生きられていないのではないかと思ってしまうわけです。
現在を犠牲にしながら、死んでいく。
つまり目的のためにA地点からB地点に「輸送」することとなんら変わりないわけです。
それに比べて「散歩」には目的がないですよね。「こんなところに花が咲いている」とか「こんなところに井戸があって川が流れている」とか。私もコロナ禍で散歩をしてみて気づくことがたくさんあったんですが、「目的」というものをいったん横に置いた時に、はじめて近くにいるひとや世界や動物、植物の関わりっていうのが見えてくるのだと感じたんですよね。つまり、ちゃんと「世界」に責任を持ってレスポンスすることができるってことですよね。
そもそも「自己責任論」って基本的におかしいんですよ。直訳すると「Self Responsibility」となるんですが、これ、おかしい英語なんですよね。「Responsibility」っていうのは「Response」という単語と関連していることからわかるように、相手に対して誠実に対応することですよね。これが「責任」を果たすことの本質です。しかし、これに「Self」がついたら「え?一体どういうこと?」となるわけです。誠実に対応する他者が欠如している。だから、そんな英語はないんです。「自己責任」を英語で考えると「at your own risk」としかいいようがない。つまり「あなたのリスクで」という言い方になるわけです。
となると自己責任よりも「責任を果たすためのレスポンス」=「真摯に応答する生成的な生き方」というのが私たちに関わってくるんじゃないかっていうのをインゴルドは言っています。
私は、そこから「生きづらさ」の問題を考えたいなと思うわけです。さまざまな問題が絡んでいるので一気に解決することは難しいんだけれど、しかしサバイバル社会で「自己責任」という世界観を脱することはできると思っています。
それは「散歩する」ことだと思います。
それは普通に散歩してもいいし、象徴的に「散歩」と使っているけれど、「レスポンスする」ということでいいと思います。目的に対する最短の道を求めるんじゃなくて、偶然性に反応する。
私の場合「来たバスに乗る」と言ってます。
つまり「来ちゃう」し、研究するにしても「疼いちゃう」んですよね。昔からそうです。目標なんてない。インドネシアから「ネシア」を取ったみたいに、来た球を打ち返してきたら、ここにいる。私は、そういう生き方もあるんじゃないかなっていう風に思うんです。
今回の「〇〇ゼミ」の根本もそうです。
わたしとみなさんとの対話の中で、少しずつ生成して変わっていくというのが目的だと思うんです。お昼に「〇〇ゼミ」のために集まったみなさんが、夕方帰る頃に何かが変わっているというのが素敵だと思うんです。
最近もてはやされている「論破」はその逆ですよね。鉄壁にして変わらないという狭い態度ですよね。
相手の意見に対して「なるほど」と思った時から変わっていく勇気を持っているのが対話や議論ですよね。少しずつ変わっていく「自分」というのを楽しむのが、みなさんが抱える「生きづらさ」を乗り越えたり、社会の「構造」から抜け出すヒントかなと、私は思うわけです。
これまでは私の授業でしたが、これから先は1時間ほど、みなさんと対話をさせていただくと思いますが、ぜひ今日の話を元に、いろいろなお話ができればと思っています。今日はみなさんありがとうございました。



あとがき
このあと、学生と中島先生の間では、それぞれの「〇〇」という穴を埋めるべく、さまざまなディスカッションや意見交換が行われました。
まるで私たちの「生きづらさ」を象徴するかのような1995年の出来事。歪んだ断層。覆る常識。圧倒的なまでの不安。そこから30年、私たちの人生と並走するかのように培われてきたのが今の社会であり、生きづらさの正体ともいえます。ただ、そこで起こるさまざまな「変化」に対して、誠実に、柔軟にレスポンスする。この「散歩」のような作業の中に、自分らしく生きるためのヒントとも言えるメッセージがあるように思いました。
例えばここで感じたことを誰かと共有してみたり、ここで思ったことをさらに深掘りしてみたり。そういう一つひとつのレスポンスが、それぞれの〇〇を埋め、明日の自分をつくるような気がします。
この記事を読んだひとは、ぜひ、まわりの友人や家族やパートナーと、「生きづらさ」について話をしてみてください。そのコミュニケーションや対話こそが、今回のゼミの目的なのです。そうやって、この社会を一緒に生き延びていきましょう。
もし、ご感想やご意見がありましたら STAND UP STUDENTS の公式インスタグラムへ DM でお送りいただくか、匿名でも投稿できるフォームにお送りください。
STAND UP STUDENTS 編集部