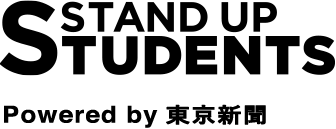01
恋とインドとヒンディー語
私はみなさんと同じ20代半ば頃、IT大国と言われながらも右傾化が進むインドで約3年間、フィールドワークをしました。インドの大学に留学するのではなく、ヒンドゥー・ナショナリストと言われるひとたちと共同生活をし、右翼的な政治宗教運動に参加する若者たちが抱える「悩み」とはなんなのかという研究をしはじめました。
ただ、実はインドが好きで行っていたわけではないんですね。むしろインド好きなひとって面倒くさそうっていう印象さえ持っていました(笑)。でもなぜインドについて学ぶことになったかというと、浪人時代に遡ります。その時に通っていた予備校で、浪人生が絶対にやってはならないことをやってしまうんですね。それは、
「恋」
です。同じ予備校のクラスの中で好きな子ができてしまい、しかも困ったことに付き合うことになるんです。完全に2浪するパターンですよね(笑)。

その子が目指していたのが大阪外国語大学(現・大阪大学外国語学部)で、当時、たいした目標もなかった私は「俺もその大学にする!」ってあっさりと志望校を変えました。外国にも外国語にも興味なかったんですが、入試の時にインドのヒンディー語専攻を選びました。
なぜ「インド」かというと、インドネシア語専攻を受験した彼女が同じクラスは嫌だというので、インドネシアから「ネシア」を取って「インドでいいや」ってなっただけなんですが、今思えばそれが人生の大きな岐路でした。何とか合格して外大に入ったのですが、とにかくインドにもヒンディー語にも興味がないので、まずはヒンディー語のデーバナーガリー文字が覚えられなくて、そのうちヒンディー語の授業に出なくなって留年するんです。全然前に進まない19歳、20歳を過ごして、その後、彼女にもフラれてしまい⋯私に残されたのは外大とインドとヒンディー語でした(笑)。


02
愛国心ってなんだっけ?
さて、ここからが本題です。 大学に入ったのが1994年なのですが、早々と留年が決まり、1995年になります。この1995年というのが現代日本にとって重要な年なんですね。まず、1月には「阪神淡路大震災」が起きました。そして3月にはオウム真理教による「地下鉄サリン事件」が起きます。突然、「若者と宗教」という問題が迫ってきました。さらに戦後50年という節目の年でしたので、当時の村山富市首相がアジアの国々に対して戦争での植民地支配と侵略に対する謝罪と反省を述べた「村山談話」を出し、国内の右派から反発を受けました。
「自虐史観なんじゃないか」
「自国の歴史に誇りを持てていないのではないか」
という声が上がり、歴史認識問題が「てこ」となって「ナショナリズム」が先鋭化してくわけです。ただ、当時の私にはピンとこなかったんですよね。「愛国心」ってどういうことだろうとなるわけです。サッカーで日本は応援するけど、私にとっては「よくわからないもの」だった。とまどいでしかなかった。そしてその「とまどい」は「私だけのものじゃないな」という直感はありました。
つまり長年の間、フタをして伏せられてきた愛国心が、戦後50年でパンドラの箱のように開いただけなんじゃないかという気がした。「どうやってこの愛国心とつき合っていけばいいの?」と、日本中がうろたえたんだと思ったんですよね。
そこで私は「知りたい!」と思うようになるんです。

私たちの「宗教に対する信仰心」や「国家に対する愛国心」とはなんなのかを、自分なりに納得して生きていきたいなと思ったんですよね。「宗教」や「ナショナリズム」が「政治」とどう関係するのか。それが研究のはじまりでした。
ここで図らずも「ヒンディー語」が役に立つことになります。
ちょうどその頃、インドが右傾化をしはじめていました。ヒンドゥー・ナショナリズムと言われる右派運動が高揚し、その運動を牽引したインド人民党が政権を奪取した。1998年のことです。バジパーイー政権の成立ですが、この政権は隣国パキスタンを威圧する形で核実験を行った。これにパキスタンが対抗して核実験を行い、南アジアが一気に緊張しました。
このニュースを見ながら、インドに行けば、大きな宗教ナショナリズムのうねりを感じることができるのではないかと思ったんです。それと同時に、戦前、若者たちが天皇を崇め、右傾化していった日本の歴史を研究することで、どういう心理状態や悩みの中で、宗教的なナショナリズムに突入していくのかが気になったんです。右傾化が進むインドと、右傾化した戦前の日本の両方を研究することで「現代の日本」というのを見ていくことができるのではないかと思い、インドへ向かうことになります。
今回の授業ではキーとなる「1995年」から戦後80年と言われる今日までの30年を振り返ることで、現代の「生きづらさ」という問題についてみなさんと考えていけたらと思います。




03
バブルの崩壊、虚構の世界
「バブル」と聞いてみなさんは何を思い浮かべますか?
みなさんが生まれる前のことですし、私は高校生だったので上の世代のひとたちがチャラチャラしているなっていうくらいの印象だったんですけれども、例えば「東京ラブストーリー」というドラマが流行ったり、「ジュリアナ東京」というディスコが流行ったりしました。「ジュリアナ東京」って、いわゆる「バブル経済」の象徴ですよね。お立ち台に若い女性たちが立って、扇子を揺らしながら踊っている光景を、バブルの象徴としてテレビで見たことがあると思います。しかし、あるおかしなことに気づくんです。「バブルの崩壊」というのは1991年4月と経済学者たちは言っているのですが、ジュリアナ東京のオープンは1991年5月なんです。なぜ「バブルの象徴」が、バブル崩壊後に誕生したのか⋯。
おそらくバブル経済は崩壊したのだけれど、戦後の右肩上がりの勢いに乗って日本人のバブリーな気分はまだ続いていたんじゃないかと考えられます。まさかその後、バブル経済が戻ることなく長い「氷河期」が来るなんて誰も認識ができなかった。つまり「きっとまた良くなるさ」とみんなが思っていた数年間があったんです。バブルは終わっているのに、バブリーな気分だけが残っているこの時期に、気づかないうちに次の時代の「生きづらさ」というのがどんどん生まれてきていたのだと私は思います。
ここで、戦後日本を代表する社会学者の見田宗介(みた・むねすけ)さんという方を紹介します。

見田さんは戦後の日本を分析するにあたって、「現実」という言葉の「反対語」が、その時代のあり方を示すのではないかと考えていました。
例えば「プレ高度経済成長期」と呼ばれた戦後から1960年頃までの「現実」の反対語は「理想」と想起されたと言います。戦争で廃墟になった街から、戦争のない理想的な街を作っていこうとしたんです。
それに対して「高度経済成長期(60年代〜70年代前半)」では現実の反対語を「夢」と捉えるようになります。「夢のマイホーム」という言葉にもあるように、届かない夢ではなくてつかめるかもしれない夢を、日本人は抱くようになります。
しかし「ポスト高度成長期」と言われる70年代後半になると、理想や夢が終わり、現実の反対語は「虚構」という言葉に変わっていきます。つまりバブルは「虚構の時代」だったと見田さんは言うわけです。「ノストラダムスの大予言」が流行し、「東京ディズニーランド」が1982年にオープン。せめて週末は「虚構世界」に身を置きたいという人が増えてくるわけです。
そんな見田宗介さんの議論を先に進めたのが、弟子にあたる社会学者の大澤真幸(おおさわ・まさち)さんでした。大澤さんは見田さんが分析した時代を「理想の時代(1945〜70年)」、「虚構の時代(1970〜95年)」と、大胆に25年単位で分けて位置づけました。「虚構の時代」は、阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件が起こった1995年には終わり、そこから「不可能性の時代」に突入したというのが大澤さんの見立てです。
では「不可能性の時代」とは何か。「現実の反対語はなんですか?」と聞かれた時に多くのひとが答えられない、答えるのが不可能な時代のことを「不可能性の時代」だと大澤さんは言っています。つまり1995年以降は「現実しかない世界」だということになります。


04
平坦な戦場でぼくらが生き延びること
そこで、90年代を代表する3つの本を紹介したいと思います。2018年に映画化されたので知っている方も多いと思いますが、岡崎京子さんによる漫画『リバーズ・エッジ』(1994年)、次に、自殺の問題を取り上げ話題となった鶴見済さんによる『完全自殺マニュアル』(1993年)、そして、小林よしのりさんが「歴史認識」や「ナショナリズム」について描いた『戦争論』(1998年)。それぞれ異なるジャンルとされている本ですが、私はこの3冊は1本の線でつながっていると思っています。
まず『リバーズ・エッジ』の中では、作品のテーマとも言える「平坦な戦場でぼくらが生き延びること」という言葉が多く登場します。生きている実感が湧かない、この社会に現実感を抱けない高校生たちが主人公の漫画です。いじめなどの社会問題に囲まれ、ただただ現実を受け止めるしかない「不可能性の時代」を「平坦な戦場」と捉え、現実社会で生き延びることを「私たちの問題」だとこの本では語っています。自分が生きているかどうかさえ希薄な登場人物たちが、話の中に登場するある「死体」を通じて「生」を実感し、「リアリティがないというリアリティ」を生きていくという作品です。今の若い世代にも通じる作品だと思いますので、ぜひ読んでみてください。
この『リバーズ・エッジ』とほぼ同時期に出版されたのが鶴見済さんによる『完全自殺マニュアル』です。
ただひたすら「自殺の仕方」が書かれた本が世に出ることでどんな社会現象が起こったかというと、いわゆるPTAなど、親が怒ったんですよね。子どもに読ませたくないと本には立ち読みができないようビニールが巻かれ、不買運動も起こりました。図書館での貸出禁止が求められたりもしました。実際にこの本を読んで自殺をしたという事件の報道もありました。

ではなぜ鶴見済さんはこの本を書いたのか。重要なのは実は自殺の方法を紹介する「中身」ではなく「まえがき」と「あとがき」にありました。
80年代後半の「世界の終わり」ブームの到来で、世界が終わる終わるとワクワクしていたけれど一向に終わらない。大きな一発なんて来ない。つまらない勉強や仕事やとりとめのない無駄話を繰り返す。そんな平坦な世界が永遠と続くのが現代社会だと言うのです。そんな中、無気力や生きている実感すら忘れてしまった私たちが、生き苦しい世の中に風穴をあけて、ちょっとでも生きやすくするために書いた本なのだと鶴見さんは言っているんですね。「死ね」というメッセージではない。「いつでも死ねる」という選択肢をポケットの中に忍ばせておくことが「生きやすさ」や「自立」につながるのではないか。そうしないと、生きている実感さえ奪われてしまうのではないか。そう鶴見さんは言っています。
「平坦な戦場でぼくらが生き延びること」にも通じますね。
『リバーズ・エッジ』も『完全自殺マニュアル』も、当時流行った「リストカット」も、「死」に直面することで「生きているリアリティ」を感じるという意味でつながっています。
このあたりから「生きづらさ」という位相が変わったのだと思います。
戦後の高度成長期を生きた人たちが言う「生きづらさ」というのは、「隣の家より貧乏だ」とか「ひもじい思いをした」とか、そういうものでしたが、90年代前半に生まれた新しい「生きづらさ」というのは、「生きている現実に現実感がない」という問題ではないかと私は思います。
戦後の象徴とも言えるコンクリートの街が壊れるなんて誰も思っていなかったのに神戸の街がぐちゃぐちゃになってしまった。日本にはテロなんてないと思っていたのに地下鉄にサリンが撒かれた。1995年に『新世紀エヴァンゲリオン』が放送開始されたのも大きな意味があったと思います。
この時期に社会学者の宮台真司(みやだい・しんじ)さんが『終わりなき日常を生きろ』という本を出します。「意味」を問う時代はとっくに終わって、それよりも「強度」、つまり「その時々の楽しさ」が重要だと言っているんですね。そしてそれを「まったり革命」とも表現しています。この世界に意味を求めるのではなくて、とにかくコミュニケーション能力を磨いて「まったり生きろ」と、当時20歳だった私のような若者たちを賞賛するんですよね。1日中ひたすら地べたに座って雑談したり、援助交際をしたり、スケボーを楽しんだりしている若者たちは今まで上の世代に怒られてきたんですが、それは「身軽さ」であり、後期近代への「適応」だと肯定し、一躍論壇のスターに昇り詰めていくんですよね。
ただ、私個人としてはその考えに反発し、生きることの意味や価値について考えてきました。宮台さんもその後、あるひとりの青年の死を受けて改めて「意味」を考えるようになるのですが、やっぱり人間って「意味」を求めるものなんじゃないのかって。だから「宗教」とか「ナショナリズム」がなくならない。世間もだんだんと「まったり生きる」というのは難しいという流れになっていきます。



05
生きづらさに対する処方箋
さて、3冊目に紹介するのは漫画家の小林よしのりさんによる『戦争論』という本です。「まったり生きる」というのが難しくなってきた時代に、先の戦争をめぐる歴史がぎっしりと文字で書かれた漫画がベストセラーになります。内容は「大東亜戦争はアジア解放のための意味ある戦いだった」という議論です。戦後タブー視されていたナショナリズムを描くことによって「おじいちゃんたちの誇りを取り戻そう」という趣旨の漫画と言えます。「日本の右傾化がはじまった」と言われるきっかけともなりました。
しかしなぜ、この本が当時の若者にこれだけ読まれることになったのか。
私は、この作品は「右派」による戦争の歴史を知ることができるという内容とは別に、若者を惹きつける要素があったのではないかと思っています。
漫画の中で小林さんは「常に死にさらされていた戦場では、国のため、公のために命を賭けるという使命感があった」「そこには生の意味と実感があった」と、鋭く時代を読んで指摘しています。つまり私はこの漫画は『リバーズ・エッジ』や『完全自殺マニュアル』の延長にあると認識しているんですね。
「生きていることにリアリティがないというリアリティ」を抱き、「平坦な戦場でぼくらが生き延びること」を使命づけられている若者たちに、「本当にそれでいいのか?」と。「国家のために」という大きな物語があった時代のことを思い出さないか?と言っているわけです。生きる意味が空洞化し、浮遊している時代だからこそ、国が「物語」を与えてきた戦争の時代を見つめ直してみないか、そして物語を肯定することで私たちの生きる意味を国民全体で取り戻そうじゃないか、というのが、この『戦争論』のメッセージなんですね。となるとこの本は単なる戦争の歴史の解釈ためにたくさんのひとに読まれたというよりは、「生きづらさ」に対する「処方箋」だったのではないかと私は思います。この本では「愛国心」「ナショナリズム」が「生きることの意味」につながると考えられたんですね。
この3つの作品から、現代の「生きづらさ」の底流となる90年代の「生きづらさ」が見えてきたと思います。後編では、みなさんが生まれる2000年以降の社会の動きを軸に、「自己責任論」や「サバイバル社会」をキーワードにひもといていきます。